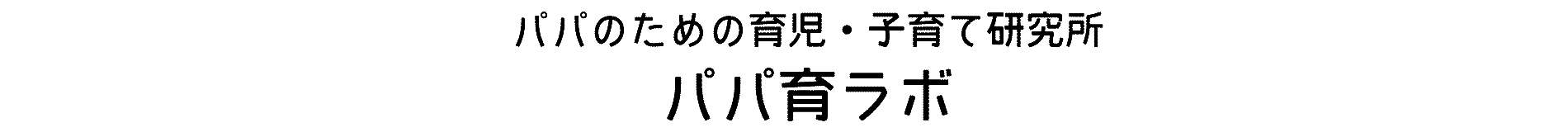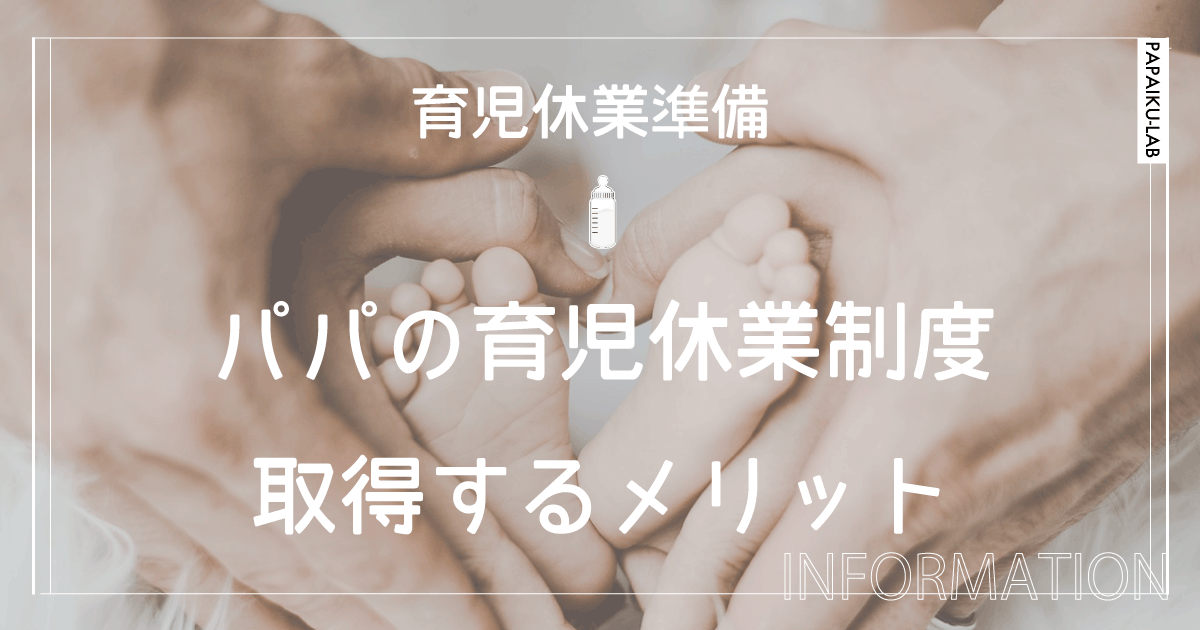こんにちは。パパ育ラボ 室長Taです。
昨今では男性育休の取得が推進され、2022年10月から新たな産後パパ育休も施工されました。
「なんとなく知っているけど…。」「取りたいけどお金が…。」
ここでは改めて男性の育休について、
制度の解説やパパが育休を取得するメリットや懸念点についてパパ視点からお伝えします。
用語や取得方法がややこしいと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが
うまく活用することで新しい家族で過ごすための大切な権利です。
ぜひこの機会にママや会社と話し合ってみてくださいね。
育児休業についてや制度や取得方法が複雑なため、概要と詳細を分けて記事にしました。
この記事では、まずパパが取得する育休の概要、次に期間やその間の経済面、最後にパパが育休を取得するメリットについてご紹介しています。
育休とは?
まずは「育児休業」の概要ついて解説します。
「育児休業」とは
「育休」とは、育児・介護休業法によって定められた労働者(給与所得者)であるパパとママが取得できる「育児休業」のこと。
出産予定日から子の1歳(状況により最長2歳)の誕生日を迎える前日まで、最大2回に分けて取得可能です。
育児休業を取得するための条件
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないこと、が明らかでないこと
育児休業の期間
ママの場合は、産前・産後は法的に働いてはいけない「産前・産後休業」がありますが、パパの場合は産休はありません。
※産休:労働基準法が定める休業制度。期間は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間。
育児休業の取得には事前の申請が必要になり、「出産予定日」を基準とします。
帝王切開や無痛分娩で出産の日取りが決まっている場合を除き、
子はいつ生まれるかわからず出産予定日より早まったり遅まったりすることはしばしばあります。
その際は、繰り上げ・繰り下げを行うことができますので申請方法の確認や会社と話しておくことが大事です。
また、子が1歳を迎える誕生日(=育児休業終了予定日)に保育所に入所できないなど、
一定の条件を満たす場合は子が1歳6ヶ月になるまで延長することも可能です。
育児休業の取得・延長の申請方法や会社に確認しておくことはこちらの記事から。
育児休業期間中のお金事情
育児休業期間の最初の6ヶ月は「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×「2/3」が、
半年以降は「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×「1/2」が支払われます。
期間中は社会保険料が免除されるため給与の約8割がカバーされる見込みとなります。
ただし、住民税は別途納める必要があります。
賃金やその申請方法についての詳細は、こちらの記事にてご紹介しています。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは
原則、子が1歳になるまで取得できる「育児休業」とは別の休業となり、
「産後パパ育休」は正式名称の通り出生時に取得するもの。
対象の期間は生後8週間までとなります。
8週間休業になるわけではなく、この8週間の間に最長4週間休業することができます。
また、4週間連続で休業することが難しい場合は2回に分けて取得できます。
2022年10月に新設されたばかりの休業制度で子が生まれても連続した期間を休業することが難しい場合に、少しの期間を分けることで取得しやすくすることを目的としています。
男性は短期間しか取得できないなど、思い込んでいる方もいるかもしれませんが、ママの仕事や保育の希望によって、パパも柔軟に取得することができます。
「育休」や「産後パパ育休(出生時育児休業)」を活用することで、分割して休業することでき、業務やキャリアのことを踏まえた育児休業を図ることができるかもしれません。
どのような期間にどのようなパターンで取得するのがよいかをこちらの記事にてご紹介しています。
ぜひ、ご夫婦やご家族、会社で話しあってみてください
パパが育児休業を取得するメリット
男性が育休をする検討する際に会社やご自身のキャリア、経済面などの理由が挙げられます。
しかし、取得することで家族への良い影響はもちろん、会社などにもメリットがあると考えられています。
男性の育児休業事情
厚生労働省が発表している「令和3年度雇用均等基本調査」では、
育児休業の取得割合を見ると、女性は85.1% 男性は13.97%とのこと。
前年までの割合と比較すると男性の育休取得率はかなり上昇しているものの、まだまだ当たり前にはなっていない状況。
日本政府は男性の育児休業取得率を2025年(令和7年)で30%にすることを目標として掲げています。
福祉や教育が豊かであることとして知られる北欧では、日本よりはるかに高い育休取得率を誇りますが、実はユニセフ(国連児童基金)が発表した『先進国における家族にやさしい政策(2019)』や
『先進国の子育て支援の現状(2021)』において、
父親のための育児休業制度については1位(41ヵ国中)となっております。
[出展:ユニセフ]
男性の育休取得率の実態はまだまだですが、制度自体は世界からも評価されています。
この記事を読んでくださっているパパで育休を取得されている方がいらっしゃるかと思います。
少数派で、色んな方(特に女性)から称賛の声をもらっていることでしょう。ましてや、
このサイトに訪れて研究されている方はほんの一握り。その姿勢でいることに誇りを持ってください。
男性が育休を取得したとしても「何をしたらよいか分からない」という声があるのも当然なのかもしれません。そんな方はこちらの記事をご参照ください。
夫婦関係にもたらす影響
一般的に結婚を機に女性の男性に対する愛情は低下すると考えられています。
さらに、出産後は特に子に対して愛情が注がれパパに対してはより一層愛情が低下します。「産後クライシス」という言葉をお聞きにならたことがあるかもしれません。
(産後のママの状態についてはこちらの記事にて解説しております。もっと知りたい方はこちらの記事を踏まえて、育休のことを検討されることをおすすめします。)
一方、育児期に愛情が回復するグループがあることもわかっています。
産後のママの身体は事故に合った後と評される産褥期(産後の回復期)の中、初めての子育てなど不安を感じている状況。
そこで、パパが家事をしてママの身体をねぎらったり、夫婦で子の成長に一喜一憂したりすることでママは「夫婦で子育てをしている実感」を得ることができ、パパへの愛情はV字回復していきます。
反対に、産後にパパが育児や家事などを率先して行ってもらえず「自分だけが子育てをしている」と感じた場合はパパへの愛情は低迷したまま。
この時期にパパへの愛情が回復されないと、そのままずっと愛情は低迷したままとなってしまいます。
今後もずっと一緒に過ごす大切なパートナーです。
パパとしても、ママから愛情を享受したい気持ちはありますよね。
また夫婦が仲良くあることで子の自己肯定感が高まり、学力も高くなる関係性もあるようです。
[出展:東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランスコンサルタント研究部長の渥美由喜(あつみなおき)氏による女性の愛情曲線]
働くことにもたらす影響
キャリアに対して不安を感じられている方もいるかもしれません。
男性社員が育児休業を長く取得できる企業ほど帰属意識や仕事への意欲が高まるというデータがあります。モチベーションが高く持てるかどうかは、今後キャリアにも影響します。
仕事を会社や同僚にお願いすることに、穴を開けることになる気がしたり後ろめたさを感じたりする方もいるかもしれません。
育休の取得を促進するために事業主に対する助成金制度があります。
「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」です。
男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性従業員が生じた事業主に支給されます。
前述の通り、男性の育休取得率はまだまだ低いため取得を促進していることやその実績があることは社外からのイメージアップにつながります。
「くるみんマーク認定(「次世代育成支援対策推進法」に基づいた制度)」や「イクメン企業アワード」などもあります。

[出展:厚生労働省『仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究』(2019)]
まとめ
今回の記事では、下記の2点について解説しました。
1.男性の育児休業について制度について
2.男性が育児休業を取得するメリットについて
男性にとっては肩身が狭かったり自分のしたいことができなかったりこれまでの自由度ではないかもしれません。
しかし、長い人生の中で子育てを一緒に行うことで、子やママの笑顔を見ることができます。
初めてぱーっと笑った表情、寝返りや立ったり歩いたりし瞬間、「あ!」と声を出した時 etc…。
数ヶ月や1年の中だけでも数えきれない多くの成長をママと共に感動することができます。
育休期間にできる隙間時間に本を読んだり映画を見たり、今後の人生について考えたりすることも可能です。
人生でそう何度も無い素敵な時間になること間違いなしです。
そのような経験がきっとパパご自身の今後の家族関係や仕事を豊かにすることでしょう。
ぜひ、当サイトをご参考に育児休業制度をご活用し、楽しいパパライフを過ごしていただけたら幸いです。